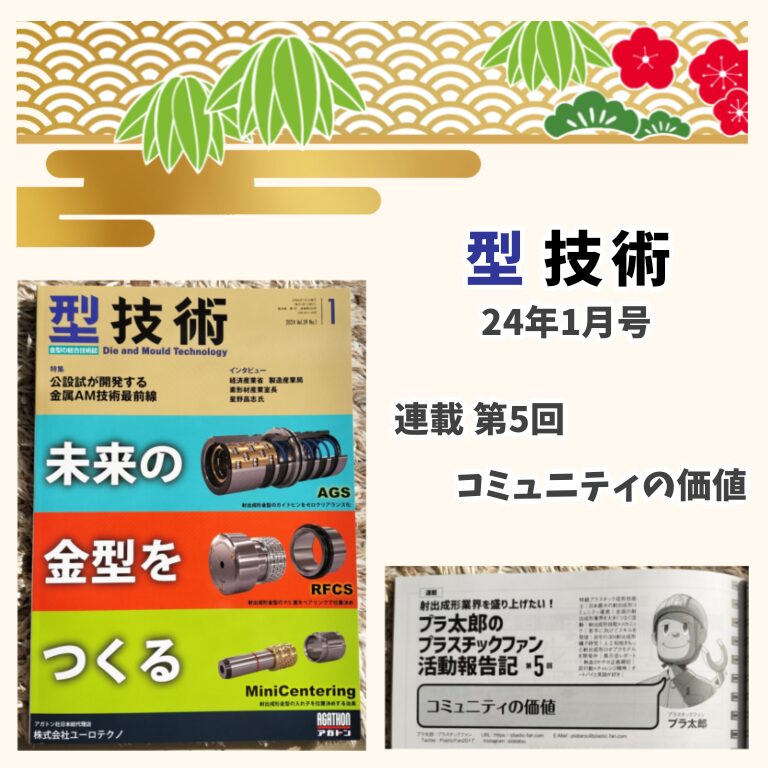射出成形の現場では人手不足が大きな問題となっています。人手不足を解消するために、射出成形作業の自動化や省人化が進められていますが、限界があります。
射出成形では、専門的な技術を要するとともに危険を伴う作業です。重大な労災事故も発生しており、安全面に関する知識が重要です。
参考
日本では少子高齢化のため、射出成形に携わることができる人が減ってきています。
このような状況の中で、「外国人技能実習制度」を利用して、外国人人材の受け入れを行う企業が出てきています。
本日は、射出成形業界の技能実習生制度導入の取り組みや課題を解説していきます。
1.技能実習制度とは
開発途上国の経済発展を担う人づくり
外国人技能実習制度とは、日本が先進国としての役割を果たすため、開発途上国に対して技術、技能、知識などの移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりを行うための制度です。
1993年に導入され、この制度によって入国した外国人は、一定期間(最長5年間)日本に滞在して、技術などを学ぶことができます。
令和4年の統計では、全国で約33万人とされています。受け入れ人数の多い国は、ベトナムが多く、全体の50%以上を占めています。次いで、インドネシア、フィリピン、中国という受け入れ人数の順番になっています。
下表 出典:出入国在留管理庁
| 国 | 割合 | |
| 1位 | ベトナム | 55.5% |
| 2位 | インドネシア | 12.0% |
| 3位 | 中国 | 11.0% |
| 4位 | フィリピン | 9.0% |
| 5位 | その他 | 12.5% |
現在、外国人技能実習制度で学べる職種・作業は、86職種・158作業です。
職種は、農業、漁業、建築、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他となっています。
プラスチック成形は、その他に分類され、射出成形はプラスチック成形という職種に含まれる4つの作業の1つです。
ポイント 射出成形作業は
「プラスチック材料を加熱し、当該成形品を作成するに適した成形条件(樹脂温・射出圧力・射出時間・射出速度・計量値・金型温度・背圧等々)を設定し、溶融されたプラスチック材料を金型の中へ高圧で充填し形を作る作業」
と定義されています。
2.実習生受け入れまでの流れ
外国人技能実習制度では、まず開発途上国の若者が技能実習生として日本の企業に就労します。
受け入れ企業は、「管理団体」と呼ばれる外部の専門機関に加入し、手続きなどを委託します。
その後、受け入れ企業は、事前に作成して監督省庁に提出した実習計画に沿って実習生の実習を行います。
プラスチック成形の場合は、実習期間が最大で5年間で、基準を満たすことで技能実習1号、2号、3号と、より高度なものに移行することができます。
技能実習には、必須業務という技能を修得するために必ず行われなければならない業務があります。
3.射出成形作業 目標と必須業務
射出成形では、必須業務として、第1号、第2号、第3号の技能実習が、下記のように定義されています。
第1号技能実習
目標:技能検定基礎級、またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格
期間:1年以内
- 射出成形機及び付属機器の操作作業
- 成形品の仕上げ加工作業
- 成形品の寸法測定作業

第2号技能実習
目標:技能検定3級、またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
期間:2年以内
- 射出成形機及び付属機器の操作、調整及び保守作業
- 材料及び金型の取扱い作業
- 成形品の良否の判定作業
- 成形品の仕上げ作業
- 成形品の寸法測定作業
- 作業記録の作成作業

第3号技能実習
目標:技能検定2級、またはこれに相当する実技実習評価試験の実技試験への合格
期間:2年以内
- 成形材料の選定作業
- 各種成形材料の予備乾燥条件設定作業
- 成形条件の設定作業
- 射出成形機及び付属機器の操作、調整及び保守作業
- 金型の取扱い及び保守作業
- 成形不良の防止作業
- 成形品の仕上げ作業
- 成形品の寸法測定作業
- 作業記録の作成作業

また、雇入れ時等の安全衛生教育や作業開始前の安全装置等の点検作業、射出成形工場における整理・整頓・清掃などの安全衛生業務も、必須業務となっています。
実習生は、就労しながらこれらの技能を習得し、技能評価試験に合格することで1号から2号、3号へと移行していきます。
4.技能実習生制度のトラブル事例
この外国人技能実習制度ですが、本来の目的は開発途上国の発展です。
しかし、日本の人手不足を補うために利用されることも多く、トラブルも起きています。
技能実習生制度のトラブル事例
- 賃金
- 長時間労働
- 単純労働要員
- 失踪
- 文化の違い
- 事件・事故
- パワハラやセクハラ など
これらのトラブルが起こってしまう要因はたくさんあります。
受け入れ企業の問題としては、低賃金や賃金の未払い、法定時間をオーバーした労働などがあります。
一方、技能実習生側の問題としては、日本語の問題、理想と現実のギャップ、悩みを相談できる人がいないなどの要因が挙げられます。
5.技能実習生制度の付き合い方
このように、文化の違う人々が一緒に働くことで、トラブルも起きやすくなりますが、制度自体は開発途上国の発展に寄与しながら、日本企業にもメリットがあるものになっています。
事前の説明や、コミュニケーションをしっかり取ること、また、困った時は外部の管理団体に相談することによって、トラブルを未然に防ぐことができます。
お互いに法律やルールをしっかりと守り、Win-winの関係でプラスチック成形の現場を発展させていくことが重要になります。