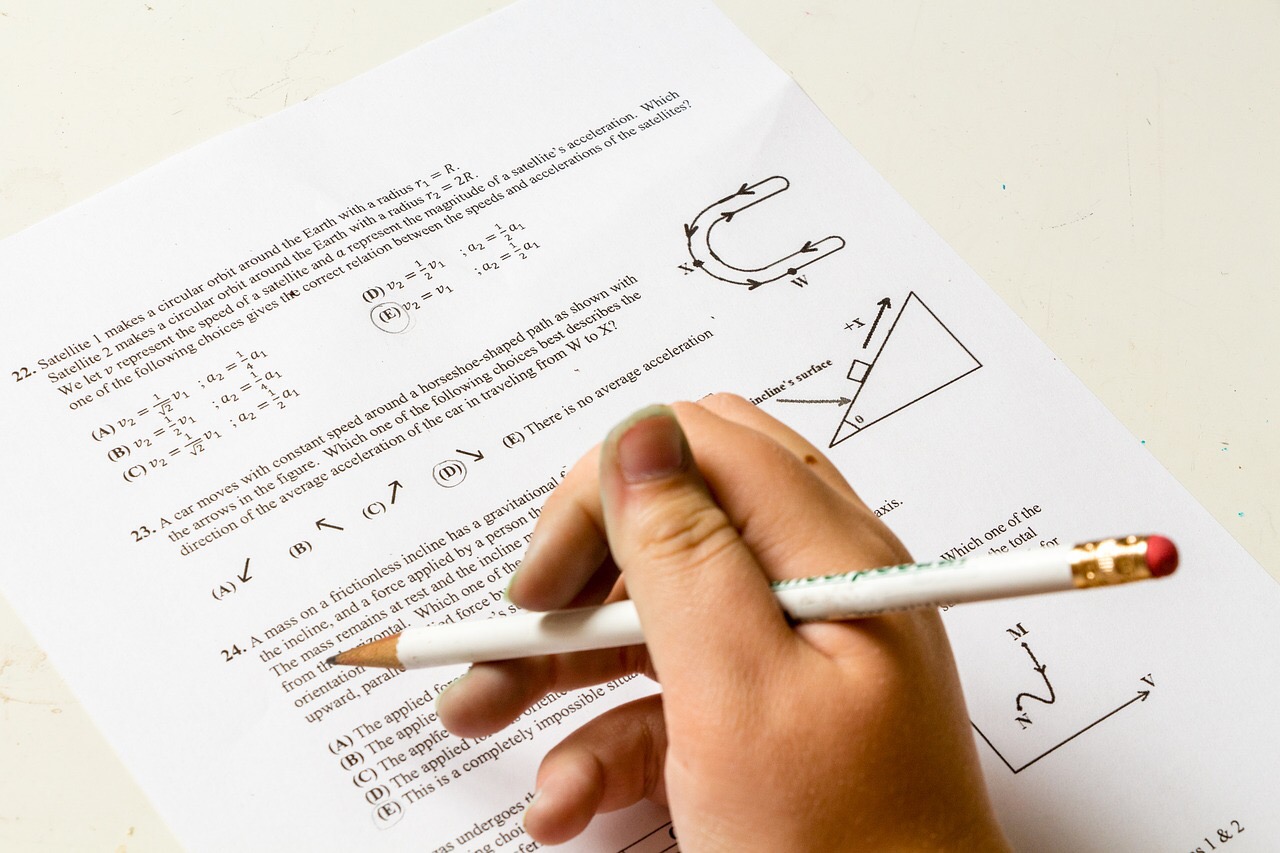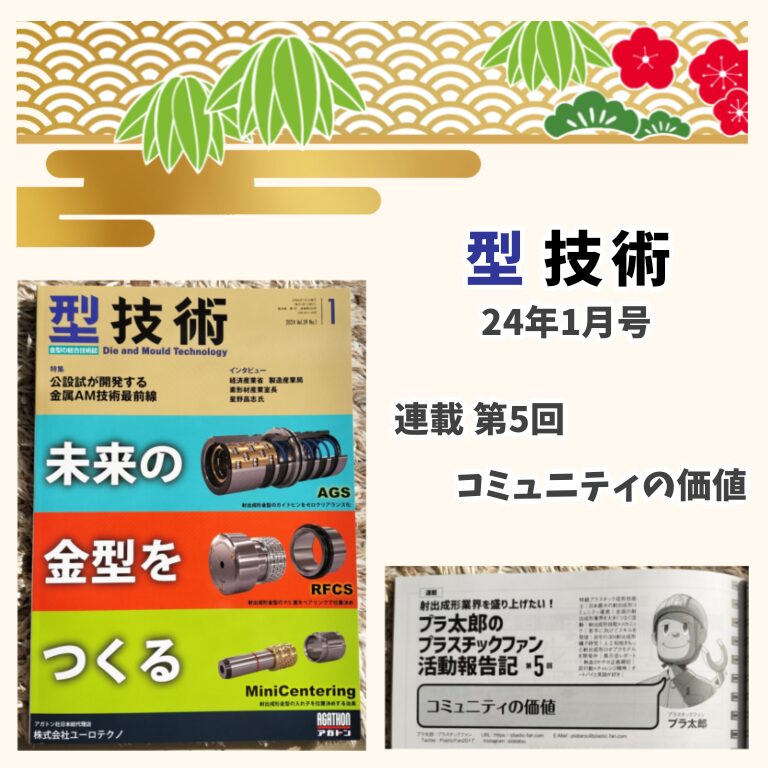技能検定 射出成形作業 学科試験 において、課題は3個
- 専門知識が必要
- 出題範囲が広い
- 勉強時間の確保 の3つです。
そして最大の敵は、睡魔です。
クタクタで帰宅後、どうしてもやる気が出ない。
本日は、【学科試験の合格】にコミットして
勉強のコツを解説して行きます。
1.学科試験 勉強のコツ
技能検定 射出成形作業 学科試験 において、対策ポイントは、3つです。
- 専門知識が必要
- 出題範囲が広い
- 勉強時間の確保
そして、最大の敵は睡魔。
試験日までの限られた時間の中で、
合格に必要な知識をいかに効率良く詰め込むかがポイントです。
技能検定に出題される科目の知識を
効率的に習得するコツを解説していきます。
(1)専門知識が必要
まず、最初に理解しておいてもらいたいことは、
「プラスチック成形=専門分野」です。
学科試験の試験勉強をせずに受験しても確実に不合格です。
初見で試験の専門性の高さに驚くと思います。
今まで学校で勉強してきた国語、数学、社会、理科、英語などの
一般教科の知識だけでは問題を解けません。
受験勉強を通して、射出成形の【知識】を身につけていく事を意識しましょう。
最初は【無知】で構いません。
過去問題 解説集を使って効率的に知識をインプットしていきましょう。
過去問題集ではなく、過去問題解説集をおすすめする理由を3つにまとめました。
- 過去問題集には、正解は「正」「誤」、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」しか書いていません。
解説集には、それぞれの問題の解説が書かれていています。 - 「プラスチック成形=専門分野」なので、間違えた問題1つ1つを、
なんで間違えたかを調べるのにすごく時間がかかります。 - 仕事で疲れて帰ってきてから、勉強するのでいかに
短時間で知識を習得するかがポイントになります。
調べているうちに、勉強がおっくうになってしまいます。
学科試験 勉強のコツ
1つ目は、過去問題 解説集を使って効率的にインプット
(ⅱ)出題範囲が広い
初心者が、陥りがちな勉強法は
- 学科試験の勉強を何から始めればいいんだろう?
- よし、プラスチックの知識を付けよう!
- 「プラスチックの基礎」「プラスチック金型設計の基本」
「プラスチックの未来」など参考書を買って、一から勉強するぞ!
さてさて、この勉強方法は、良いと思いますか?
プラスチック成形の基礎を学ぶことは良い事です。
しかし、学科試験の勉強方法としては、非効率です。
試験日まで、勉強期間は限られています。
広い試験範囲をカバーするためには、
試験に出る知識を効率的に学習していきましょう。
過去問題は5回解くと、ほぼ内容がインプットされます。
【過去問の解き方 参考】
- 1回分を解いてみよう。時間がかかってもいいです。
- 間違えた問題は解説書を参考にする。
- そして、違う年の問題を解いて、解説書で理解を深める。
3~5年分の過去問を、「解いて、解説を読んで理解を深める」を、5周繰り返す。
【過去問を解いていく習熟度】は下記の通りです。
- 1周目:専門用語が多く、問題を解くにも時間がかかる。
何が何だかわからない状態。 - 2~3週目:なんとなく頭に入ってきているレベル。
- 4週目:問題を暗記できるレベルで、ほぼ100点。
応用が利く。 - 5周目:問題の意図が理解でき、出題者側のひっかけに気付ける様になる。
これは実際私が過去問を解いて体感したリアルなデータです。
勉強を進めていく参考にして下さい。
ここでポイントになるのが、合格点は65点。
合格点が65点/100点ですので、
33問/50問を正解する必要があります。
まずは、学科試験の試験科目割合を見てください。
| 試験科目 | 割合(%) |
| 1.共通 | 10% |
| 2.成形法 | 30~40% |
| 3.成形機 | 15~20% |
| 4.金型 | 10~20% |
| 5.材料 | 10~20% |
| 6.関連JIS | 4% |
| 7.製図 | 3% |
| 8.関連法令 | 4% |
【1.共通】~【5.材料】までの、
出題割合が高い事がわかります。
反対に、【6.関連JIS】~【8.関連法令】は、低いです。
合格点を取る為には、出題割合の高い科目を重点的に勉強しましょう。
満点を取る必要はありません。
高校受験の様に、上位〇〇%が合格でもありません。
合格点を目指しましょう。
学科試験 勉強のコツ
2つ目は、合格点65点を目指す
(ⅲ)勉強時間の確保
仕事をしながら技能検定の勉強をするのは、とても大変です。

まとまった時間はなかなか取れません。
休日は、家族と過ごしたり、友達と遊んだり忙しいものです。
本ウェブサイト内に、学科試験の過去問題解説ページを用意しております。
仕事の休憩時間や、通勤時間など5分、10分の隙間時間を活用して
知識の習得に役立てて下さい。
学科試験 勉強のコツ
3つ目は、スキマ時間を有効に使う
(Ⅳ)睡魔との戦い
クタクタで仕事から帰ってからの勉強は正直しんどい。
勉強しなければ、合格できない。
でも、眠い。
「なんでおれ技能士受験したんだろ。。。」と、
投げやりになる気持ち共感します。
私も、ブラック企業に務めながら受験勉強しました。
やはり最大の敵は睡魔です。
眠い時の勉強法をシェアしていきます。
睡魔に勝つ方法
①仮眠
一番のおすすめは、仮眠です。
15〜20分が最適です。
少し仮眠を取るだけで、一時的に眠気はスッキリします。
私の実体験からのデータでは、
30分〜1時間寝ると、寝起きがボケます。
更に、二度寝して、気づいたら朝になってます。
②立って勉強
座って、机で勉強するから眠くなる。
立って、ウロウロすれば多少睡魔は紛れます。
どうしても今日こそは勉強しなきゃ。
そんな日に眠くなったら試して下さい。
③朝勉
朝少し早起きして勉強するのもおすすめです。
夜中は、身体が疲れているのでどうしても睡魔に勝てません。
朝方にシフトチェンジすることで、
体力のある時間帯に勉強することができます。
④思い切って寝る
あまりにも疲れている時は、
いくら勉強しても入ってきません。
諦めて寝ましょう。
そして、翌日は5分でも良いから絶対に勉強をしましょう。
おすすめしないこと
①エナジードリンク
これは、私の個人的な意見です。
眠気を覚ますドリンクを飲んでも、眠いものは眠いです。
結局、勉強するのは、自分の意思です。
マインドで勝たなくては勉強しても入ってきません。
②無理して続ける
睡魔はとても強敵です。
どんなことをしても眠いものは眠い。
頭を振ったり、足をつねったり、頬をビンタしたり。
一瞬は目が覚めますが、その5秒後すぐに眠くなってしまうものです。
そんな状態で無理して続けても、まったく入ってきません。
仮眠を取っても、立って眠気を覚ましても、だめなら諦めて寝ましょう。
5.まとめ
学科試験に出る知識を効率的に学習することが重要です。
学科試験は、勉強しないで受験したら落ちます。
しっかりと受験対策をしましょう。
下記リンクから参考書、参考記事をシェアしています。